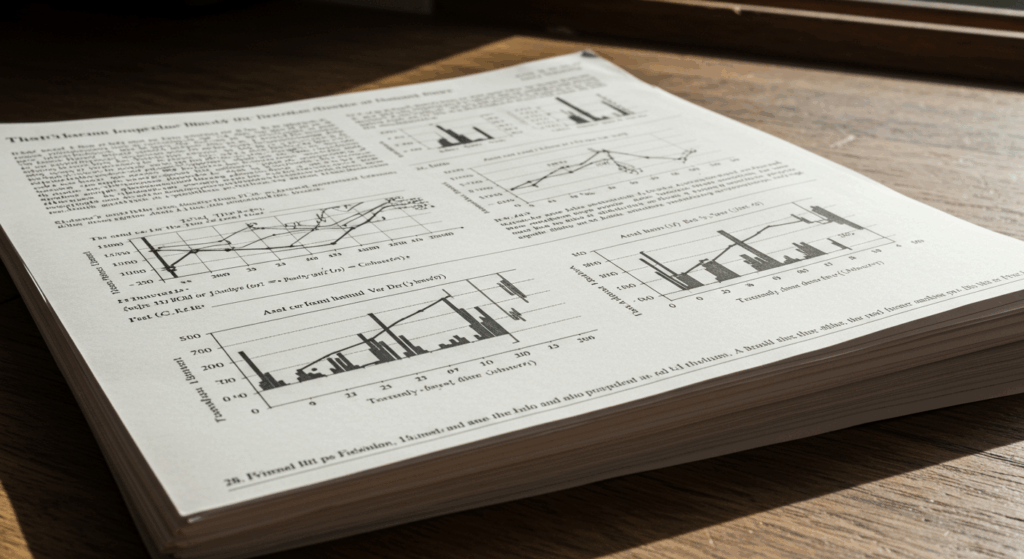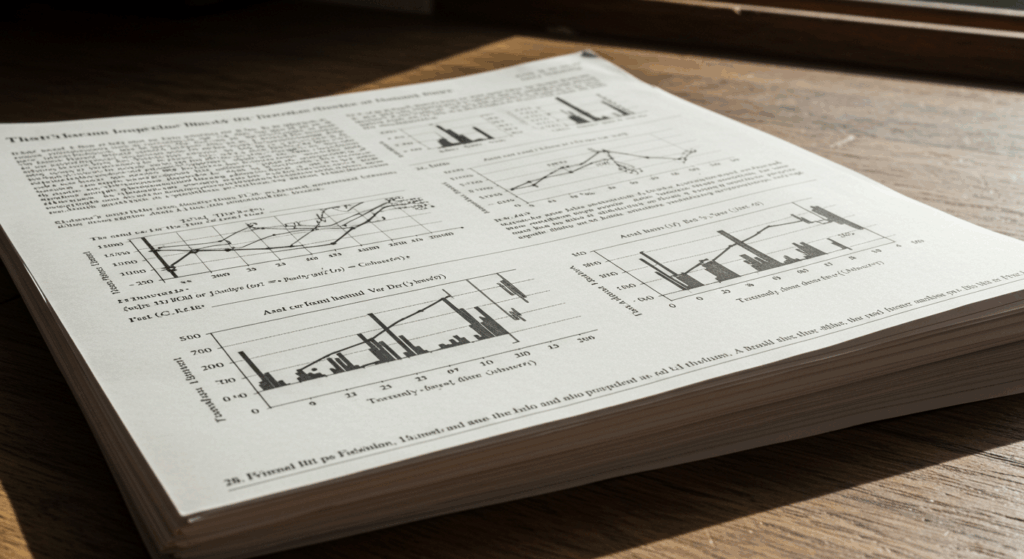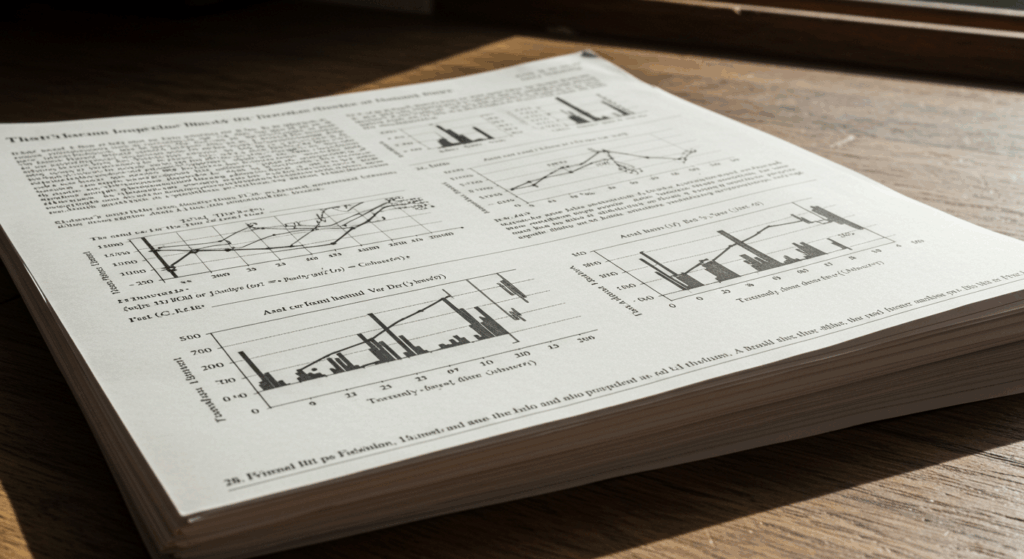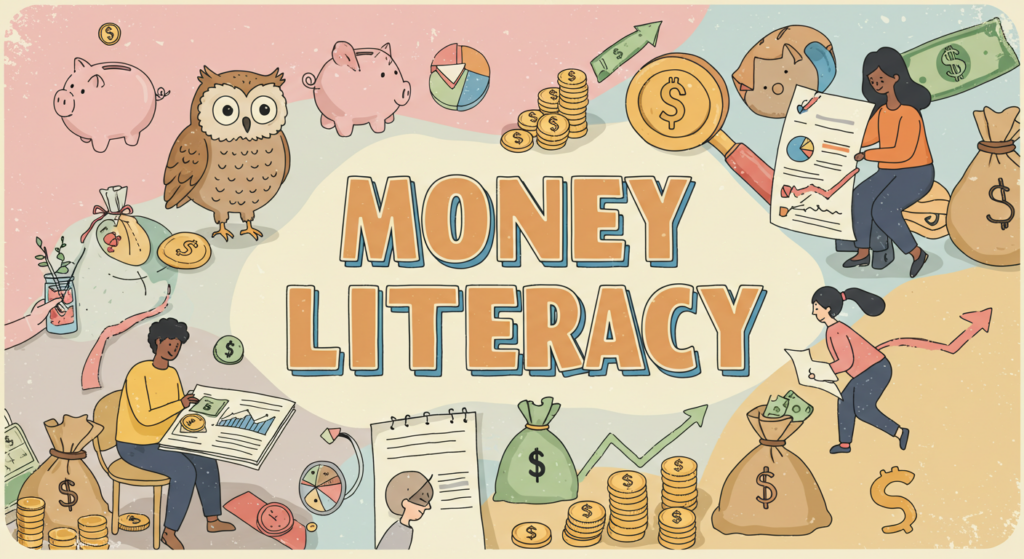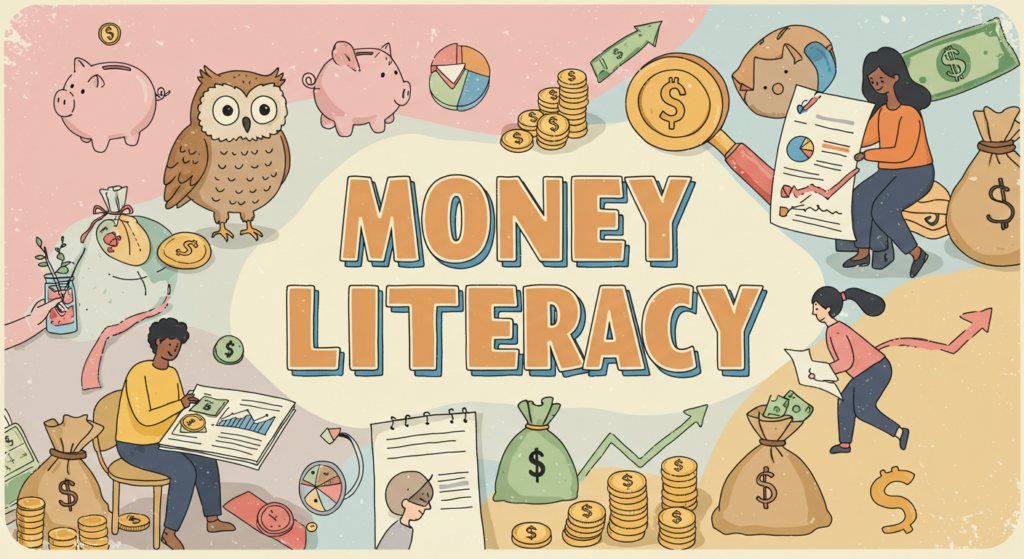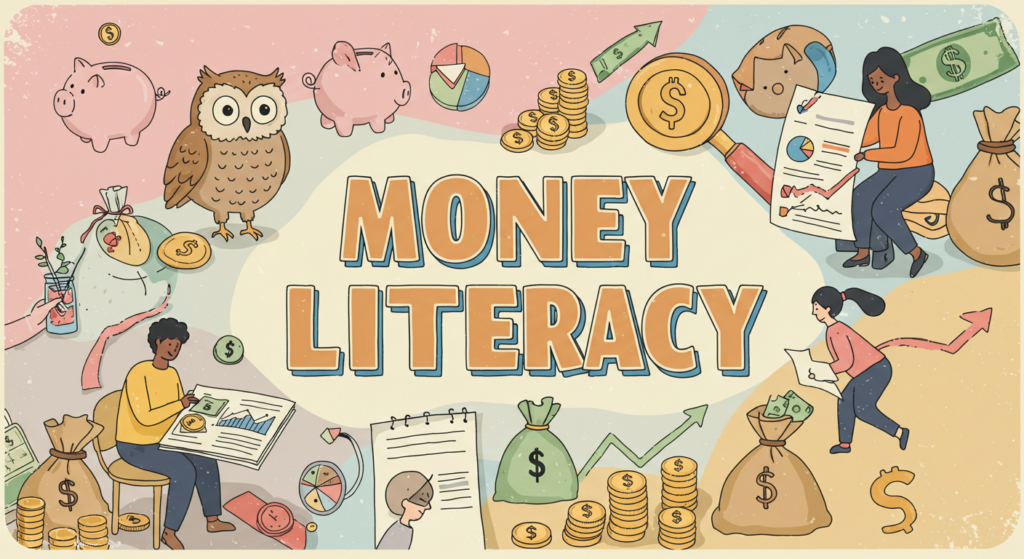
問題点:なぜおこづかい制は良くないのか?
多くのご家庭では、子どもに毎月決まった額のおこづかいを渡す「おこづかい制」を採用しています。しかし、これにはいくつかの落とし穴があります。
- 「お金はもらうもの」という思考が身につく
- おこづかい制では、「何もしなくても毎月一定額がもらえる」ため、子どもが「お金は労働しなくても手に入るもの」と誤解する可能性があります。これは、大人になってからの「タダでお金が手に入らないかな」という発想につながる恐れがあります。子供の頃の思考のクセが取れていない状態です。
- おこづかいは、性質的に会社員としての固定給のような考え方に近く、自らお金を生み出す発想が育ちにくくなります。(会社員思考)
- 「お金を生み出す力」が養われない
- おこづかいをもらうだけでは、「お金をどうやって得るのか?」という視点が欠けます。
- 実社会では、労働収入以外にも「価値を提供することでお金を得る」「投資によってお金を増やす」などの方法がありますが、それを学ぶ機会が少なくなります。
- 「お金を管理する経験」が不足する
- 毎月一定額がもらえる環境では、「足りなくなったらまた来月もらえばいい」と考えるようになり、お金を計画的に使う意識が薄くなることがあります。
- 結果として、社会に出たときに「収入の管理ができない」「衝動買いをしてしまう」といった問題が生じる可能性があります。
- 「お金の価値を実感しにくい」
- 自分で苦労して稼いだお金と、親から何もしなくてももらったお金では、使い方に違いが出ます。
- 「お金は簡単に手に入る」と思うと、無駄遣いしやすくなります。
こうした問題を防ぐためには、「お金は努力や工夫の結果として得られるもの」という考え方を育てることが重要です。
おこづかい制の代替案:「お金を生み出す力」を育てる方法
おこづかい制の代わりに、子ども自身が「お金を得る経験」をする仕組みを作ることで、実社会で役立つマネーリテラシーを育てることができます。
1. 成果型報酬制:「価値を提供するとお金が入る」経験をさせる
おこづかいを無条件に渡すのではなく、「何かしらの価値を提供したら報酬がもらえる」仕組みにすると、お金の本質を理解しやすくなります。
✅ 家の手伝いを「労働報酬制」ではなく「価値提供制」にする
- 「皿洗いをしたら100円」ではなく、「家族が助かるような特別な仕事をしたら報酬を得られる」ようにする。
- 例:「お母さんが忙しい日に料理を作る」「お父さんの仕事の資料を整理する」など。
(「労働報酬制」と「価値提供制」は、違いが分かりにくいと思うので章末で捕捉します。)
✅ 期間限定のチャレンジ制度を導入する
- 「1週間で500円を稼ぐためにどうするか?」を考えさせる。
- 例:リサイクル活動(ペットボトルを集めてリサイクル業者に売る)、知人(家族、親族でOKです)に自分のスキルを提供する(年賀状のデザイン、手作りアクセサリーなど)。
2. 投資型おこづかい:「お金を増やす経験」をさせる
「もらったお金をそのまま使うのではなく、どう活かせば増えるのか?」を学ばせる。
✅ 親が「銀行役」になり、利子をつける
- 「今1000円持っているけど、1ヶ月使わなかったら5%増やすよ」というルールを作る。
- 「お金は使うだけでなく、増やせる」という視点を育てる。
✅ プチビジネスの体験
- 「1000円を元手に、どうやって増やすか?」を考えさせる。
- 例:「文房具を大量に仕入れて、クラスメイトに小売りする」「オリジナルくじ引きを作って販売する」。
(友達、クラスメイトとの関係が気になるようであれば、「家族の欲しがっているものを子どもがリサーチして仕入れてきて、家族に販売する」といった形でもよいです。)
3. お金の管理体験:「一定額を自分で運用する経験」
毎月決まった額を渡すのではなく、「自分でお金を管理する力」を育てる仕組みにする。
✅ 「予算管理ゲーム」を導入する
- 例:「1ヶ月間で3000円を自由に使っていい。ただし、それ以上は追加なし。」
- おこづかいの代わりに渡す。その月はおこづかいはあげない。(その代わり普段のおこづかい以上のお金を渡す。)
- 「1ヶ月」といった期間を設定する。使わなかった分は両親が回収する。
- 「足りなくなったらどうするか?」を考える習慣をつける。
- 「無駄遣いして後悔する経験」をさせることで、金銭感覚が磨かれる。
- 「有意義に使えた部分」や「無駄な支出だった部分」など、一緒に振り返りをする。
もし難しいようであれば、「おこづかい帳」の導入と、「親子で振り返りの時間を作る」といった感じでもOK!
✅ 既存の金銭管理サービスを利用する。
シャトル株式会社「シャトルペイ」
- 子ども向けのVisaプリペイドカードとアプリが連動した、親子で使えるデジタルマネー管理サービス。
- 子どもが自分で使った金額をアプリで“見える化”でき、金銭感覚が育つ。
三井住友カード「かぞくのおさいふ」
- 親が子どもに対してチャージ・利用制限ができるVisaプリペイドカード型のファミリーファイナンスサービス。
- 親が使い道を把握・制限できるため、安心して“予算管理の習慣”を教えられる。
NTTドコモ「comotto(コモット)」
- おこづかい管理と家族間のコミュニケーションを融合した、お金の教育アプリ。
- 「お金を得る・使う・振り返る」プロセスを通じて、家族で“対話しながら学べる”仕組みを提供。
どのサービスも、金銭管理や金融教育について深く学べるアプリ・コンテンツなので、気になったら使ってみてはいかがでしょうか。
✅ 「寄付文化」を取り入れる
- 「得たお金の一部を、社会のために使う経験」をさせる。
- 例:「この100円を誰かのために使うとしたらどうする?」
- 「お金は自分だけのためではなく、人のためにも使えるもの」と伝える。
- それによりお金の価値をより強く感じられるようになる。
まとめ:「おこづかい制」ではなく「お金を得る経験」をさせよう!
✅ おこづかい制の問題点
- 「お金はもらうもの」という思考が身につく
- 「お金を生み出す力」が育たない
- 「お金の管理能力」が身につかない
- 「お金の価値を実感しにくい」
✅ 代替案としての方法
- 成果型報酬制:「価値を提供するとお金が入る」経験をさせる
- 投資型おこづかい:「お金を増やす経験」をさせる
- お金の管理体験:「一定額を自分で運用する経験」を積ませる
これらを取り入れることで、子どもは「お金は努力や工夫の結果として得られるもの」と理解し、将来的に「お金を生み出す力」と「お金を管理する力」を兼ね備えた大人へと成長していくでしょう。
次章では、「お金のためにしか動かない子どもにしない工夫」について掘り下げていきます。
(補足)「労働報酬制」と「価値提供制」の違い
「労働報酬制」と「価値提供制」の違いと具体例
1. 「労働報酬制」とは?
労働報酬制とは、「作業を行った対価として報酬をもらう仕組み」のことです。
決められた仕事をこなすことで、あらかじめ決められたお金を受け取るという形になります。
「時間」や「労力」に応じた報酬が発生するため、アルバイトや会社員の給与の考え方に近いです。
✅ 具体例
- 皿洗い1回=100円(単純な作業に対する報酬)
- 部屋の掃除=200円(時間と労力に応じた対価)
- ペットの世話=300円(一定の責任を伴う仕事)
📌 特徴
- ルールが明確で、親子ともに管理がしやすい
- 労働時間が増えれば報酬も増える仕組み
- しかし、「言われたことだけをやる」受動的なマインドになりがち
2. 「価値提供制」とは?
価値提供制とは、「作業そのものではなく、それによって生まれた価値に対して報酬を受け取る仕組み」です。
「人に役立つことをした結果として、お金が入る」という考え方に基づいています。
✅ 具体例
- 家族が助かるような工夫をする → 報酬が発生する
- 例:「お母さんが忙しい日に料理を作る」
- 例:「お父さんの書類整理を手伝い、効率を上げる」
- 例:「おばあちゃんのスマホ設定をして、使いやすくする」
- 問題を解決するアイデアを出す → 報酬が発生する
- 例:「家の中の片付けを楽にする方法を考え、実行する」
- 例:「弟が勉強しやすくなる学習スペースを作る」
- 人を喜ばせる → 報酬が発生する
- 例:「おじいちゃんに手作りの写真アルバムを作ってあげる」
- 例:「家族みんなが笑顔になるようなイベントを企画する」
📌 特徴
- 子どもが主体的に考えたことを実践する。
- 「どうすれば人に役立つか?」を考える習慣が身につく。
- ただの労働ではなく、「創造力」「課題解決力」を活かすことが求められる。
- 「お金を得るために工夫する」経験を積むことで、将来の起業や自立の力につながる。
3. 「価値提供制」を実践するためのポイント
「労働報酬制」は簡単に導入できる仕組みですが、「価値提供制」に移行するには工夫が必要です。
✅ 導入のコツ
- 「何をすれば報酬がもらえるのか?」を一緒に考える
- 「どんなことをすれば家族が助かる?」
- 「どんなアイデアがあれば、生活が便利になる?」
→ 子どもに考えさせ、主体性を育む!
- 報酬の基準を明確にする
- 「ただ手伝ったらOK」ではなく、「成果が出たら報酬を渡す」仕組みにする
- 例:「料理を作る」→「家族が美味しいと感じたら報酬」
- 「ありがとうの価値」を報酬の一部にする
- お金だけでなく、感謝の言葉や特別なご褒美(好きな遊びの時間など)を加える
📌 最初は労働報酬制+価値提供制を組み合わせながら、徐々に価値提供制にシフトすると良い!
短期的な結果を求めるなら「労働報酬制」、長期的に考えるなら「価値提供制」が有効!
最初は「労働報酬制」を取り入れつつ、徐々に「価値提供制」にシフトすることで、
子どもが主体的に 「どうすれば価値を生み出せるか?」 を考えられるようになります。
「お金はもらうものではなく、価値を生み出すことで得られるもの」
この意識を子どもに持たせることで、将来、お金に困らない大人へと成長できるでしょう!🔥
(PR)