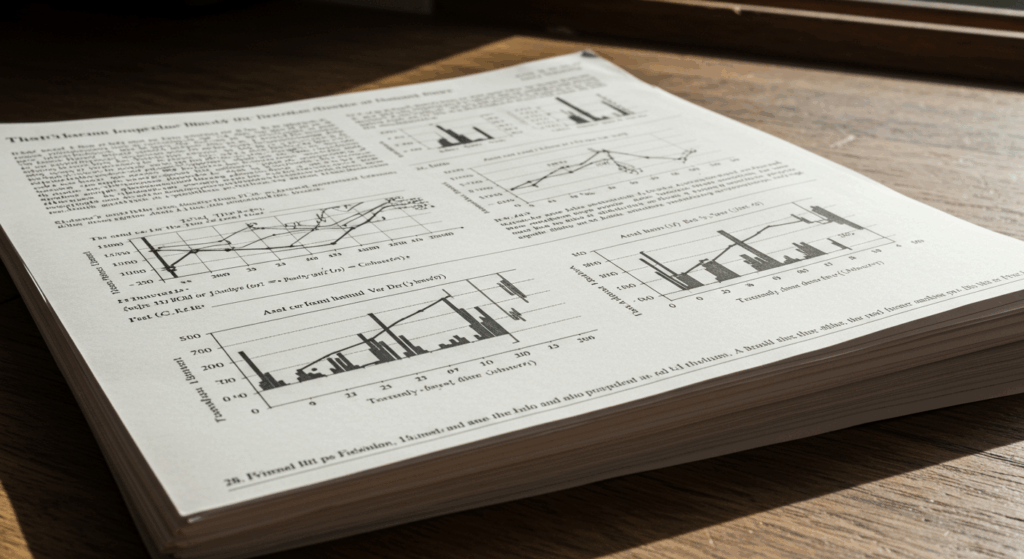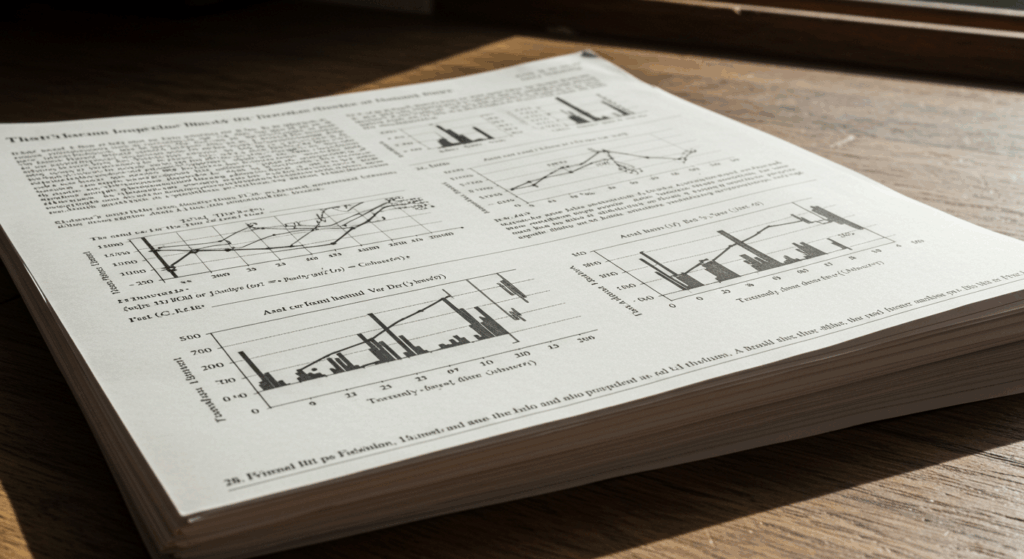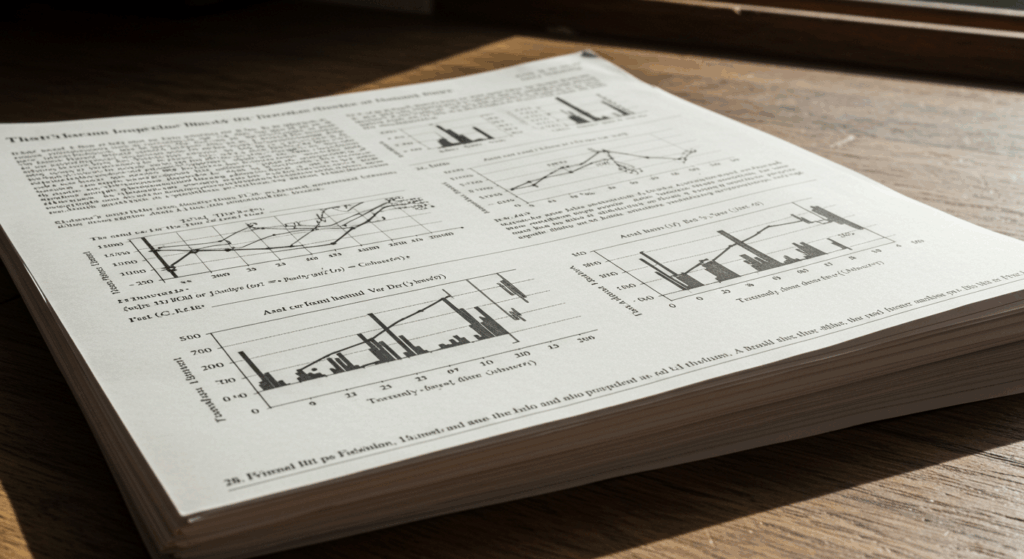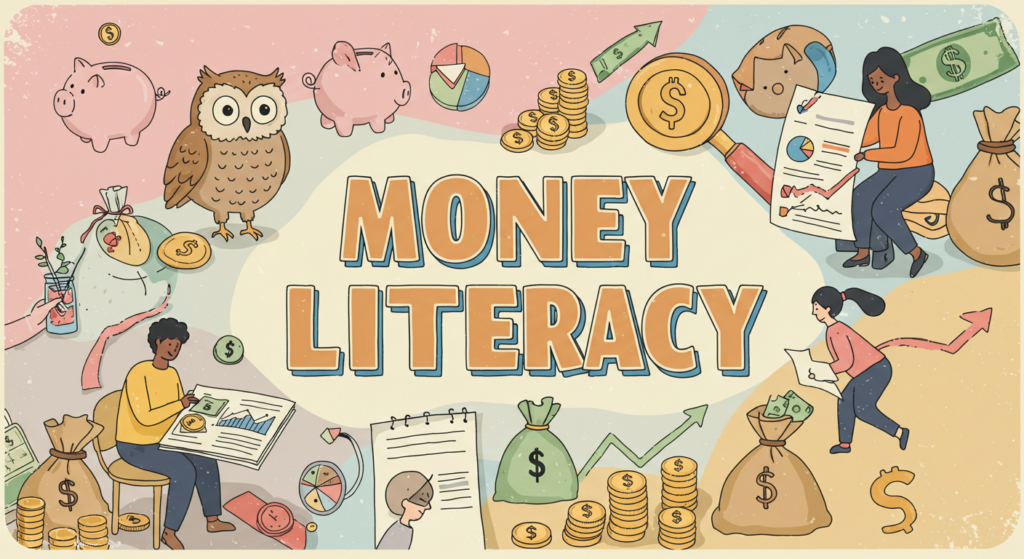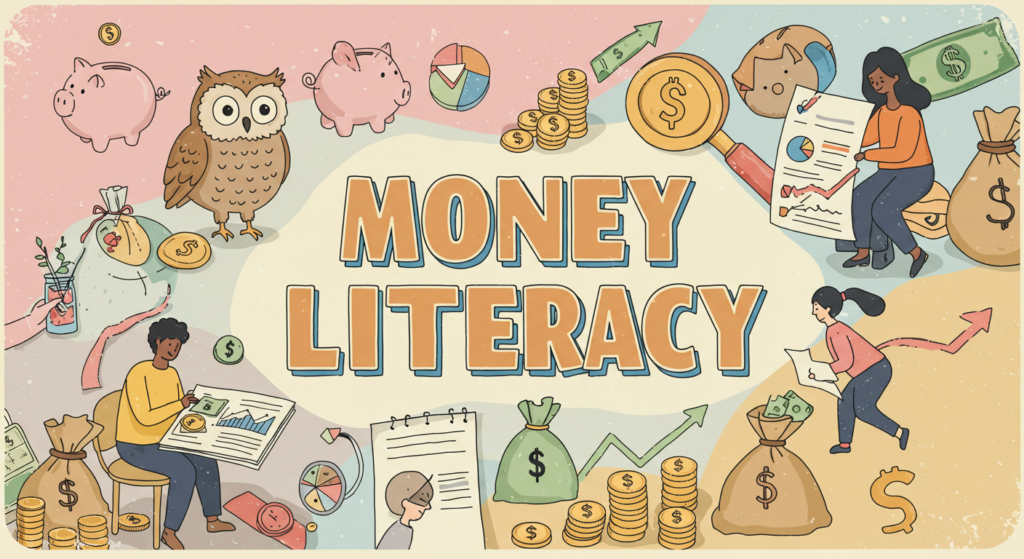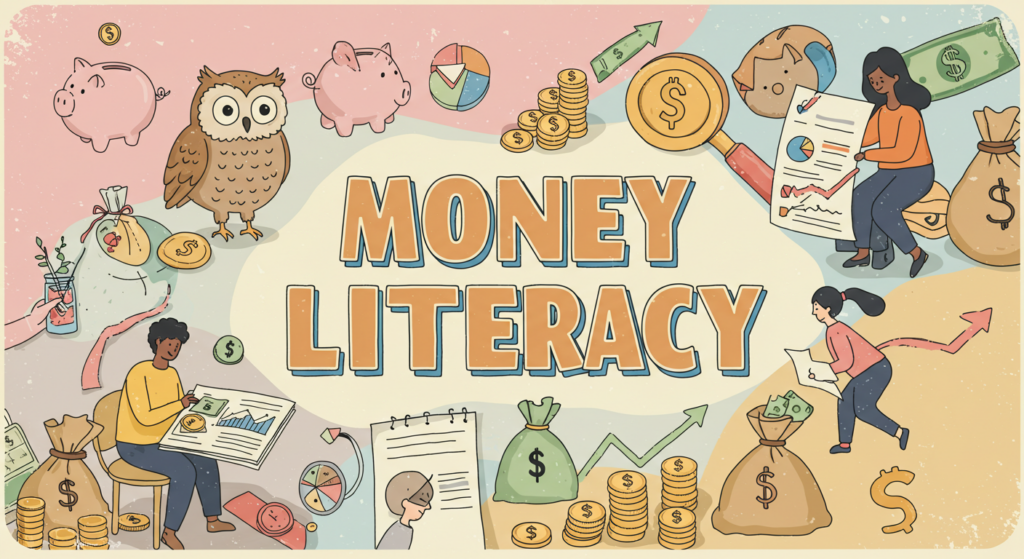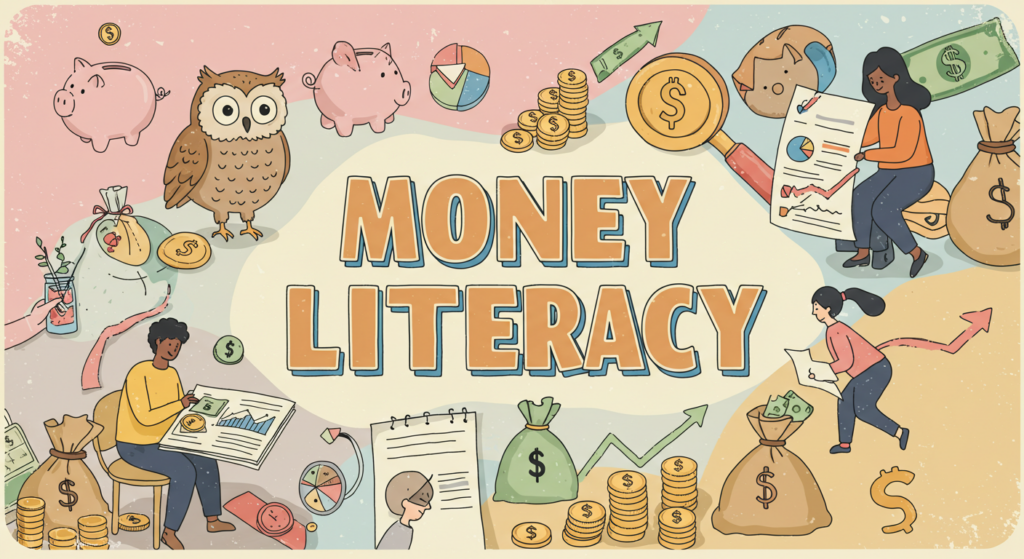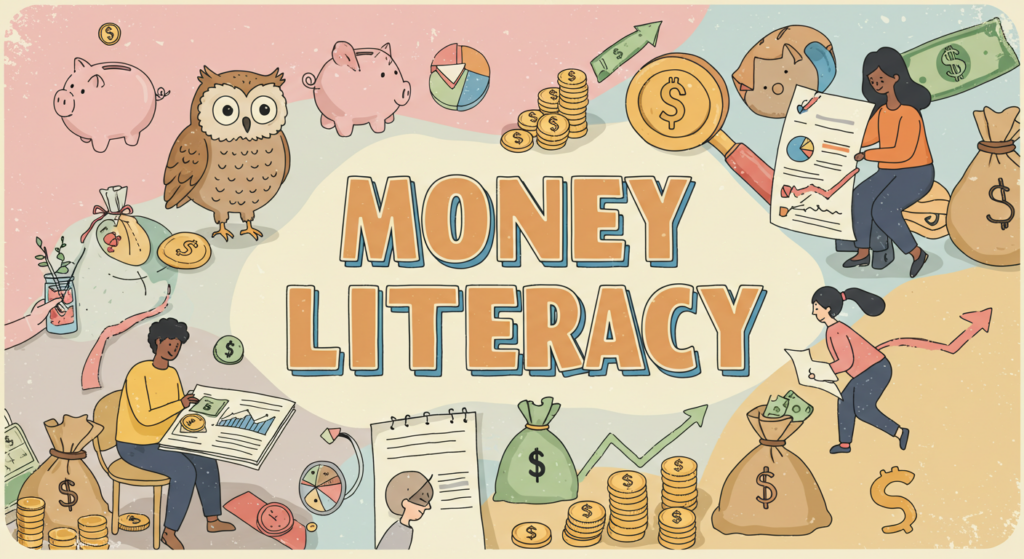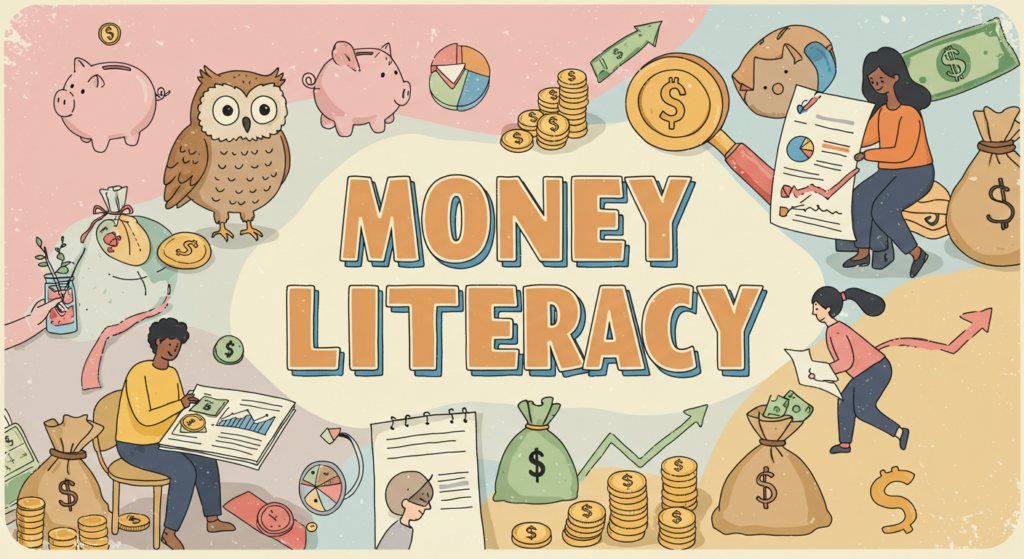
子どもに「お金を得る経験」をさせる意義
お金の教育の目的は、「お金は労働の対価」という単純な考え方を超えて、 「価値を提供すればお金が生まれる」という視点を育てることです。
「お小遣い制」のように親からもらうのではなく、 子ども自身が 「工夫してお金を得る」 体験を積むことで、
- お金の価値を実感する
- 創造力や問題解決力を身につける
- お金の管理・投資の感覚を育てる
といったスキルを身につけることができます。
前章で触れた「お金を生み出す経験」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
1. 手作り商品を売る:価値を提供する体験
✅ 実践アイデア
- 折り紙アートやイラストを販売する
- 手作りアクセサリーやキーホルダーを作って販売する
- 自作の「くじ引き」や「謎解きゲーム」を作って遊ばせる(有料制)
✅ 学べること
- 「原価」と「売値」の概念
- どんなものが人に求められるか?を考える力
- お金を得るためには「価値を提供する」必要があると理解できる
2. 貸し出しビジネス:物の価値を知る体験
✅ 実践アイデア
- 漫画やゲームを1日〇円で友達に貸す
- 学校で使う文房具や便利グッズのレンタルサービス
- 自宅にあるレアなアイテムを「特別な日に貸し出し」
✅ 学べること
- 「お金を使わずに収入を得る」経験
- 「持っているものに価値をつける」発想
- 「貸し手と借り手の信頼関係」の重要性
3. 家の中で「ビジネス的手伝い」をする
✅ 実践アイデア
- いつものお手伝いではなく、「特別な価値提供」に報酬を出す。 例:「家族のために特別な料理を作る」「パソコンの設定を手伝う」
- お金をもらうだけでなく、「ありがとうポイント」を貯める仕組みにする。
(「ありがとうポイント」については第三章で述べます。)
✅ 学べること
- 「単なる労働ではなく、価値提供が大事」と学べる
- お金だけでなく「感謝」も報酬になる
- 「仕事の交渉」の基本(どのくらいの価値があるのか?)
4. 貯金の利子を体験する:投資の基本を学ぶ
✅ 実践アイデア
- 「親が銀行役」になり、子どもの貯金に利子をつける 例:「1か月500円を預けたら、10円の利子をつけて返す」
- 使う vs 貯める vs 増やす のバランスを考えさせる
✅ 学べること
- お金は「増やす」ことができると知る
- 「時間が経つと増える」投資の概念を体感
- 「貯金しすぎても機会損失がある」ことを理解する
5. お金を増やすチャレンジをする
✅ 実践アイデア
- 1,000円を渡し、「1週間でどこまで増やせるか?」ゲームをする 例:
- 100円で仕入れたお菓子を150円で売る
- 家にあるものを再利用して価値を生み出す
- 失敗してもOK!お金をどう動かすかを考えさせる
✅ 学べること
- お金の増やし方は無限にあると実感する
- 失敗を通じて、次の戦略を考える力がつく
- 「お金は使うだけではなく、生み出すもの」と理解できる
6. 寄付や社会貢献の体験:「お金の使い方」を学ぶ
✅ 実践アイデア
- 自分が得たお金の一部を寄付する経験をさせる 例:「100円を使って誰かを幸せにするには?」と考えさせる
- 「プレゼント文化」を作る 例:自分で稼いだお金で家族や友達にプレゼントを買う
✅ 学べること
- 「お金は自分のためだけに使うものではない」と学べる
- 「お金の価値は、使い方で変わる」と理解できる
- 「社会に貢献する喜び」を体感する
まとめ:「お金を生み出す経験」を積ませる重要性
✅ なぜお小遣いをもらうのではなく、「お金を得る経験」が大事なのか?
- 「お金はもらうものではなく、価値の対価として生まれる」と理解できる
- 「どうすればお金を生み出せるか?」を考える創造力が育つ
- 「お金の使い方」「増やし方」「人のために使うこと」も学べる
これらの経験を通じて、子どもは 「お金を稼ぐ力」+「お金を管理する力」+「お金を活かす力」 をバランスよく学ぶことができます。
次章では、「お金のためにしか動かない子どもにしないための工夫」について掘り下げていきます。
(PR)